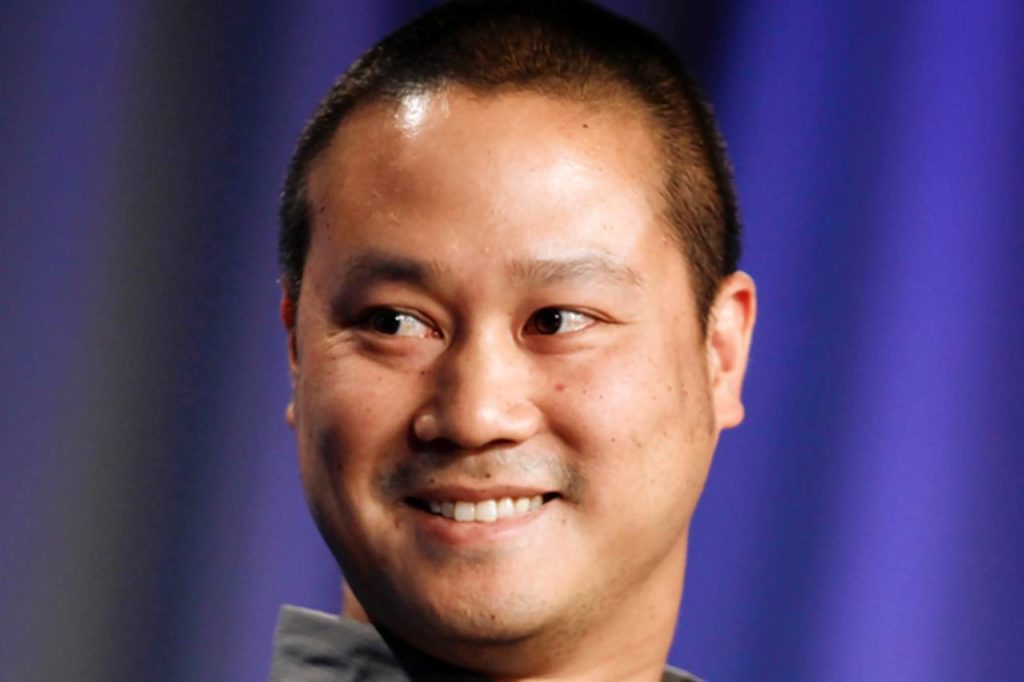家族信託における受託者の任務は、死亡や辞任などにより終了します。
それでは、受託者が不在になると、信託自体も終了してしまうのでしょうか。
もし受託者がいなくなると同時に信託も終了するのであれば、安心して信託できませんよね。
また、受託者がいない状態が続いても信託が終了しないとなると、それはそれで困ります。
そのため、信託法では、受託者が不在になった場合のルールを決めています。
そのルールは、「受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が一年間継続したとき」に信託は終了するというもの。(信託法第163条第3号)
つまり、1年以内に新しい受託者が選任されると、信託は終了することなく継続します。
後任の受託者を決めておけば、受託者が亡くなった場合でも慌てる必要はありません。
信託が長期間にわたる可能性がある場合や、受託者が高齢の場合、新受託者を定めておくと安心です。
以下では、受託者の任務終了や、信託の終了について細かく見ていきます。
受託者の任務が終了するケース
受託者の任務が終了するのは、死亡や辞任の場合だけではありません。
信託法では、以下のように受託者の任務終了事由が定められています。
一 受託者である個人の死亡
二 受託者である個人が後見開始又は保佐開始の審判を受けたこと。
三 受託者(破産手続開始の決定により解散するものを除く。)が破産手続開始の決定を受けたこと。
四 受託者である法人が合併以外の理由により解散したこと。
五 次条の規定による受託者の辞任
六 第五十八条の規定による受託者の解任
七 信託行為において定めた事由
2 受託者である法人が合併をした場合における合併後存続する法人又は合併により設立する法人は、受託者の任務を引き継ぐものとする。受託者である法人が分割をした場合における分割により受託者としての権利義務を承継する法人も、同様とする。
3 前項の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
4 第一項第三号に掲げる事由が生じた場合において、同項ただし書の定めにより受託者の任務が終了しないときは、受託者の職務は、破産者が行う。
5 受託者の任務は、受託者が再生手続開始の決定を受けたことによっては、終了しない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
6 前項本文に規定する場合において、管財人があるときは、受託者の職務の遂行並びに信託財産に属する財産の管理及び処分をする権利は、管財人に専属する。保全管理人があるときも、同様とする。
7 前二項の規定は、受託者が更生手続開始の決定を受けた場合について準用する。この場合において、前項中「管財人があるとき」とあるのは、「管財人があるとき(会社更生法第七十四条第二項(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四十七条及び第二百十三条において準用する場合を含む。)の期間を除く。)」と読み替えるものとする。
つまり、個人である受託者の後見開始審判や、解任でも任務が終了します。
受託者が個人である場合、死亡や後見開始のリスクがあるため、受託者を法人にすると有効です。
すべてに共通するのは、「受託者が信託事務を行える状態ではないことが客観的に明白になった場合」という点です。
受託者の辞任は制限される
辞任によっても受託者の任務は終了しますが、受託者の辞任には制限があります。
辞任の制限とは、「原則、受託者が辞任をするためには、委託者及び受益者の同意を得る必要がある」というもの。
委託者及び受益者の同意が求められるのは、受託者には信任義務があるためです。
委託者の財産管理を任された受託者が、自由に辞任できるとなると法律関係が安定しません。
では、委託者及び受益者の同意が得られない場合、どうすればいいでしょうか。
委託者及び受益者の同意を得られない場合、受託者は裁判所の許可により辞任が可能です。
2 受託者は、やむを得ない事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。
3 受託者は、前項の許可の申立てをする場合には、その原因となる事実を疎明しなければならない。
4 第二項の許可の申立てを却下する裁判には、理由を付さなければならない。
5 第二項の規定による辞任の許可の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
6 委託者が現に存しない場合には、第一項本文の規定は、適用しない。
受託者の任務終了により、新たな受託者はどうやって選任される?
受託者の任務が終了した場合、新しい受託者はどのように選任されるのでしょうか。
新たな受託者は、以下のような方法により選任されます。(信託法第62条)
2.信託によってあらかじめ定めた方法により選任する方法
3.委託者及び受益者の合意によって定める方法
4.利害関係人の申し立てにより、裁判所が選任する方法
上記1.2の、「信託によってあらかじめ定めている場合」は、その定めに従います。
しかし、あらかじめ定めた受託者がすでに死亡している場合や、候補者が就任を拒否するケースもあるかもしれません。
もし上記1.2の「信託によってあらかじめ定めた方法」でも新受託者が決まらない場合、上記3の「委託者及び受益者の合意」により新受託者を定めることができます。
そのため、いきなり委託者及び受益者の合意で新受託者を決められるわけではありませんのでご注意ください。
なお、上記4の「利害関係人の申立による裁判所の選任」は、必要があると認められた場合しか認められません。
裁判所が受託者を選任する義務はなく、裁判所が必要がないと判断した場合、新受託者は選任されない可能性もあります。
このように、新受託者を選任するのには難航も予想されます。
信託を利用する際は、もしもの場合の受託者をどうするか、綿密な計画を立てることが大切です。
新受託者が就任したときは、新受託者は、前受託者の任務が終了した時に、その時に存する信託に関する権利義務を前受託者から承継したものとみなされます。(信託法第75条)
信託が終了するケースとは?
信託の終了事由は、以下のように定められています。
二 受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が一年間継続したとき。
三 受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が一年間継続したとき。
四 受託者が第五十二条(第五十三条第二項及び第五十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により信託を終了させたとき。
五 信託の併合がされたとき。
六 第百六十五条又は第百六十六条の規定により信託の終了を命ずる裁判があったとき。
七 信託財産についての破産手続開始の決定があったとき。
八 委託者が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた場合において、破産法第五十三条第一項、民事再生法第四十九条第一項又は会社更生法第六十一条第一項(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四十一条第一項及び第二百六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による信託契約の解除がされたとき。
九 信託行為において定めた事由が生じたとき。
(委託者及び受益者の合意等による信託の終了)
2 委託者及び受益者が受託者に不利な時期に信託を終了したときは、委託者及び受益者は、受託者の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
3 前二項の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
4 委託者が現に存しない場合には、第一項及び第二項の規定は、適用しない。
信託の終了事由が発生すると、受託者は清算受託者として、清算手続を行います。(信託法第177条)
清算が結了するまでは、信託は存続するものとみなされます。(信託法第176条)
[getpost id=”2037″ title=”関連記事” ][getpost id=”1755″ title=”関連記事” ][getpost id=”1761″ title=”関連記事” ]